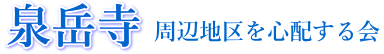地権者の合意形成なき再開発?
*事業者のやり方は地権者にとり著しく不公正・不公平だとして多くの地権者が「同意」に難色を示しており、このままでは合意形成は成り立ちません。
*そこで事業者が考えたのが、近隣にJR新駅が2020年3月に開業することに乗じ、新駅から国道15号線をまたぎ再開発区域まで「歩行者用デッキ」を自ら設置することを条件に、行政に再開発を認めさせようとする構想です。
*そしてこれを正当化させるために、地権者とは関係のない周辺地域の住民を動員して決定権者である「港区」へ都市計画決定を行うよう要望書を提出させたのでしょう。事実とすれば極めて不適切であり、多くの地権者はこの行動を、「地権者が同意しないのならば周辺住民を動員してでも都市計画決定を実行するぞと言う事業者側の意思の表れ」だと捉えています。
地権者の合意形成なき再開発などありえるのか?
*「YES」でもあり「NO」でもあると言えます。
*第1段階の「都市計画決定」は区の行政判断であり、実は同意率に関しての法的要件はありません(港区の場合、区は事業者に対し「概ね8割の地権者同意」を取得するよう行政指導を行ってはいるものの、これは必要
条件ではありません)準備組合はこの点に着目して「歩行者デッキ」を自ら設置することを大義名分に都市計画決定を実行させようと画策しているものと思われます。
さてここで「地権者の合意形成なき都市計画決定」はありえるのか? この場合は港区の裁量となるのでYesもあり得ます。
*一方、たとえ都市計画決定が実行されたとしても次段階の「本組合設立」においては、「地権者の2/3の同意」を含む諸条件が法により厳格に定められています。ここで地権者が同意を行わなければ再開発を進めることはできません。法律がこれを許さないのです。
*仮に地権者を軽視する形で区が「都市計画決定」を実行したとなれば、地権者の猛反発は必至です。場合によっては住民運動も起きかねず、また区の判断も問われることになり、当然、組合設立も難航することになります。
さてこの場合「地権者の合意形成なき組合設立」はありえるのか? 答えはNoです。
無責任さを露呈した準備組合
*事業者側が発行した「準備組合ニュース2019年12月号」では、周辺の町会長から「デッキ設置に向けて激励の言葉をいただいた」ことを誇示する一方で、デッキ設置を事業者側が行うとなった場合、建設費や管理費に関して地権者がどのような影響を受けるのかについての記述が一切ありません。(都合の悪い話には触れたくはないのでしょう)
後日、この点を地権者グループが準備組合に常駐する住友商事社員2名へ問いただしたものの、「建設費や維持費を誰が負担するのかは現時点では白紙」との回答しか返って来なかった由。
*白紙のまま都市計画決定を実行されたら地権者はたまりません!無責任ではないでしょうか?これが今の準備組合の実態なのです!
歩行者デッキ設置が地権者へもたらす影響…
*そもそも歩行者デッキはJR新駅の利用者の利便性向上のための公共設備。それをなぜ再開発区域の地権者260名(彼らの計算式では32名)が主導し負担リスクを負ってまでこれを設置しなければならないのか?
地権者への事前相談もなく、どう考えても全くおかしな話なのです。
*歩行者デッキともなると建設費や維持費もかなりの額となり、もしこれを再開発組合が自ら設置するとなれば、一部は補助金で充当できたとしても、費用の大半は組合(=地権者)負担となる可能性が高いのです。
*このことはつまり、権利変換時における地権者の持ち床面積が減ってしまう可能性があることを意味します。
例えば、権利変換時に100平米の床を貰えると見込んでいた地権者が、実際には70平米しか貰えないと言ったことが起きるのです。後日、事業者へ「話が違う!」と抗議したところで、書面による保証を取り付けていない限り結局は押し切られてしまいます。それどころか「100平米ほしいのなら不足する30平米分は購入してほしい」などとたたみ込まれます。過去の再開発事例でも多くの地権者がこのような扱いを事業者から受けています。
(都市計画決定が実行される前に事業者側から「書面による保証」を取り付けておくことの重要性はそこにあります。)
まとめ
まだ準備組合が上記のシナリオ通りに再開発を進めると確認されたわけではありませんが、その様な動きがあることは事実です。地権者の大切な資産や権利が毀損する懸念がある以上、事業者側には事前の説明責任があります。
秘密裏に事を進めるなどあってはなりません。
先日、地権者グループが準備組合に常駐する住友不動産の社員2名に対し「デッキ設置費用」の負担先に関する質問を投げかけたにも係わらず、彼らは「まだ白紙」としか答えませんでした。
白紙なのにデッキ設置の話はどんどん進めているのです。
これが果たして彼らが標榜する「皆さまの準備組合」、「地権者主導の再開発」だと言えるのでしょうか?
「良い話はするが、悪い話はしたがらない」、「重要な問題に正面から向き合おうとしない」、「質問してもなかなか答えてくれない」、「口頭で答えても、書面では出したがらない」…
その様な姿勢の準備組合であれば不要です!
さて皆さまの地域の準備組合は如何でしょうか?