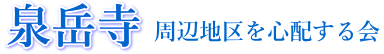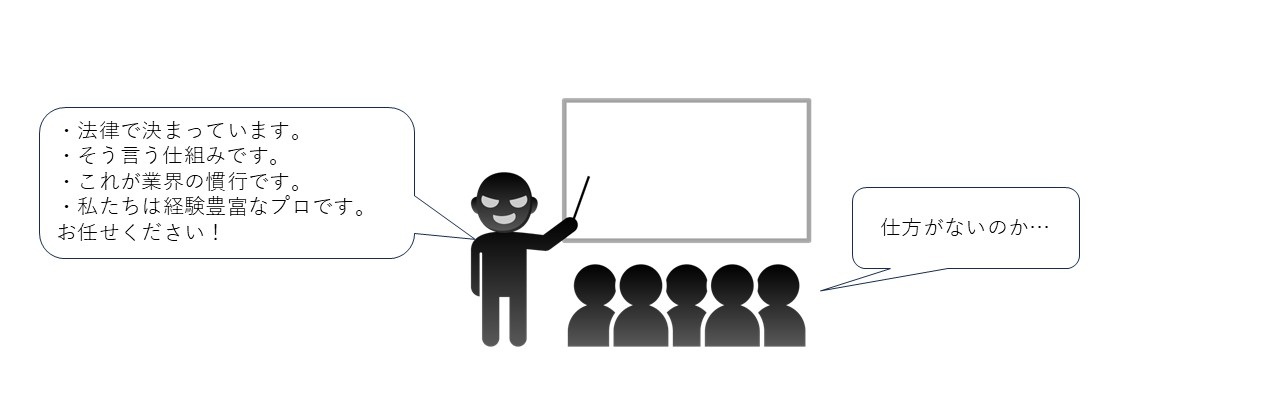
前トピックス(264)では再開発業者側による「朝三暮四」的な説明を取り上げましたが、本トピックスでは業者側が地権者に対して発する「誤った説明」を取り上げ、注意喚起を行います。(注1)
(注1)ここで言う「業者」とは、住友不動産や三菱地所など一部の再開発業者に加え、これらの業者の意向を忖度して行動するコンサルや鑑定士なども含めるものとします。
1. 業者はなぜ「誤った説明」を行うのか?
2. 地権者が知っておくべきこと
3. 「誤った説明」(よくある4つのパターン)
4. まとめ
業者はなぜ「誤った説明」を行うのか?
一言で言えば、
業者側は地権者を正論で説得することが出来ないため、
「誤った説明」や「玉虫色の説明」を行ってでも
地権者を説き伏せて自社利益の最大化に繋げようとするから
だと考えられます。
近年、地権者側も再開発の知識を身に付けるようになり、「物言う株主」ならぬ「物言う地権者」も増えつつありますが、それでもまだ地権者の多くは再開発知識に疎いと言う現実があります。
業者側はこの状況を逆手に取り、専門用語や制度を駆使しながら地権者を煙に巻き、「不利な条件」をあたかもそれが法律や制度であるかの如く説明することで地権者を強引に説き伏せようとしますので注意が必要です。
地権者が知っておくべきこと
地権者は先ず、
「再開発業者」と「地権者」とは互いに利益相反関係にある
と言う実態を知っておく必要があります。更にその上で、再開発業者側は、地権者の利益よりも自分たちの保留床面積(=開発利益)の最大化を優先させようと行動する点も併せてお知り置きください。
再開発ビルの総床面積 = 権利床面積 + 保留床面積
ですから、「保留床面積」が増えればその分「権利床面積」は減り、逆に「保留床面積」が減ればその分「権利床面積」は増えると言った具合に、最終的には「再開発業者」と「地権者」とは互いに床面積を取り合う関係に陥ることになります。(注2)
(注2)再開発業者は日頃から自らを「事業協力者」と称し地権者に寄り添う姿勢を演出しますが、その彼らも再開発の最終段階になれば保留床を購入する「参加組合員」へと姿かたちを変え、地権者の利益相反相手へと変貌するのです!「飼い犬に手を噛まれる」とは正にこのことを言うのではないでしょうか?
床の配分をめぐり両者が対等な立場で協議出来れば良いのですが、現実はそう簡単ではありません。多くの現場では再開発業者側が一方的に主導権を握り、自社寄りのコンサルや鑑定士を使い、不適切な手段を講じてでも「保留床面積」(=開発利益)の最大化を図ろうとする実態が各地で確認されています。
その際に彼らが使うのが地権者を惑わす「誤った説明」なのです。
「誤った説明」(よくある4つのパターン)
百戦錬磨の再開発業者(コンサルや鑑定士等を含む)は一般地権者が再開発の知識にさほど詳しくはない点に着目し、敢えて専門用語や制度を持ち出すことで、「地権者側に不利な条件」を当然であるかの如く押し付けて来るので地権者は要注意です。
以下では、よくある4つの誘導パターンを紹介して参ります。
【事例①】
「保留床単価は原価床単価である」
これは「地権者の犠牲のもとで業者が儲ける」ための詭弁です。
過去から何度も説明して来た通り、再開発業者の目論見は「激安保留床単価」を既成事実化させ保留床面積(=開発利益)の最大化を図る点にあります。業者側が説明する「原価ベースの床単価」は正にその「激安保留床単価」を正当化させるためのロジックですのでご注意ください。
再開発では事業費の不足額を再開発業者側が「保留床処分金」名目で支払い、その対価として保留床を獲得する仕組みですが、保留床処分金の額は一定ですから、「保留床単価」が低いほど保留床面積は増えて業者が得をする反面、権利床面積はその分減るので地権者は損をします。
そこで何としてでも「激安の保留床単価を実現したい」と考える一部の再開発業者はコンサルや鑑定士などを使い、
「保留床単価は事業原価(即ち、事業費+従前評価額)
から算出される原価床単価とするのが一般的である」
などとあたかもそれが既定のルールであるかの如く説明を行うのです。
しかしこれは実際の市況や近隣の分譲相場を完全に無視した考えであり、もしこのロジックを認めれば市場相場から大きく乖離した「激安保留床単価」が誕生することになり、地権者の権利床面積を大きく減らす結果を招きますので地権者は要注意です。
地権者は「原価だから仕方がない」という言葉には決して惑わされず、常に業者側が提示する「保留床単価」が妥当なのかを冷静に見極めることが何よりも大切です。(注3)
(注3)住友不動産や三菱地所と言った一部の再開発業者が提示して来る「近隣相場の半値以下」と言った激安保留床単価には特にご注意ください。適正な保留床単価は、例えばタワマンの場合、近隣地区の同等物件の販売価格の70~80%が妥当な水準だと言われており、国土交通省も一般論としながらも書面にてこの水準を是認しています。
【事例②】
「従前評価に開発利益は加味されない」
都市再開発法には、従前の土地・建物の権利変換についての規定(第80条)はあっても、開発利益(注4)についての規定は存在しません。
この点に着目し、一部の鑑定士などが「都市再開発法第80条」を根拠に「容積緩和による開発利益は従前評価に加味されない」などと主張してくることがあります。しかし、本当にその通りなのでしょうか?
開発利益を加味するか否かに関しては「肯定説」と「否定説」が存在しますが、都市再開発法に規定が存在しない以上、その方針を決める権限は事業主体である再開発組合側(=地権者側)にあります。
事業主体でもない再開発業者側が「開発利益は加味されない」などと勝手に断定する権限など実は最初から存在しないのです。
「法律で禁止されている」、「そういう仕組みだ」、「それが慣行だ」などと言った「実態とは異なる説明」を行うことで、地権者に不利な条件を「仕方がない」として受諾させるのは、業者側の意向を忖度した鑑定士やコンサルなどが好んで使う手口ですので、地権者の皆さまはくれぐれもお気を付けください。
(注4)開発利益とは再開発事業の容積率緩和に伴う土地価格の上昇分を言います。再開発ビルで新たに創出される莫大な面積の床は開発利益の源泉だと言えます。
【事例③】
「従前評価額が還元率を決める」
業者の意向を忖度したコンサルなどが「従前評価と等価交換で権利床が与えられる」などと強調する場合があります。
あたかも従前評価額の高低が還元率を決める要因であるかのように装う手口ですが、これは「誤った説明」ですのでお気を付けください!
業者側の真の目的は、このような説明を行うことで地権者の関心を従前評価へと仕向け、保留床単価の妥当性(=激安保留床単価)に地権者の関心が向かわぬようにすることにあると考えられます。
そもそも還元率の計算式は、
還元率= (総専有面積-保留床処分額÷保留床単価)÷従前床面積
ですから、還元率を決める要因として重要なのは「保留床単価」であり、「従前評価額」でないことは一目瞭然です。
この様な業者側の「誤った説明」にはくれぐれもお気を付けください。
【事例④】
「増床は特別分譲扱いとなる」
これは地権者の「増床」を制限したい業者側が使う詭弁の一つです。
業者が激安単価で床を購入できるのなら、地権者だってその単価で床を買い増したいと考えて当然です。しかし、地権者による購入を許してしまうと、再開発事業者が得る保留床面積(=開発利益)はその分減ってしまいます。そこで業者は様々な理屈を駆使することで地権者に「増床制限」をかけようとしますが、中でも地権者の増床意欲を削ぐのに効果的だと業者側が考えるのが「増床は特別分譲扱いとなる」と言う誤った説明です。
このことをもう少し詳しく説明します。
一般に「増床」とは地権者が権利床と一体の区画を、有償で追加取得する床を言うのに対し、「特定分譲床」は地権者や第三者が権利床とは別の区画を有償で追加取得する床を言います。
業者側は増床を特定分譲床扱い(=保留床の転売)だと説明することで、結果として、組合が一旦取得した保留床の処分方法を定めた「都市再開発法第108条」が適用となり、取得に際して「公募」や「再開発組合の決議」を経る必要が生じ、また別途売買契約書の締結も必要となり、更には印紙税までかかる等、地権者の当然の権利である「増床」をあたかも「複雑でリスクがある行為」であるかのように演出し、地権者を増床断念の方向へ誘導しようとするのです。当然これらは業者側が発すべき正しい説明ではありません。
実際には、権利床と同一区画の増床は「権利変換計画書」に記載して権利床と一体的に扱うことが組合の判断で可能です。
それにもかかわらず、最初から「原則できない」と断じるような業者側の説明は、地権者の選択肢を狭めるだけでなく、地権者の権利そのものを制限しようとする悪質な行為であると言わざるを得ません。
まとめ
今回は、地権者を欺く「誤った説明」として代表的な4つのパターンを取り上げました。何れの事例も、業者側が「法律で決まっている」、「そう言う仕組みだ」、「業界の慣行だ」などと言う言葉を用いて地権者を誤った方向へ誘導しようとする点で共通しています。
しかし、よくよく考えて見れば、
再開発(第一種市街地再開発事業)は最終的には
組合の総意(=地権者の総意)で運営されるもの
です。
事業主体でもない業者側には、「誤った説明」を通じて自社に有利な内容を正当化させようとする資格も権限も最初から無いのです。
従い、地権者としては再開発業者(コンサル、鑑定士等を含む)の一方的な説明を決して鵜呑みにせず、法令と事業計画の内容を理解した上で、自身で適切に判断して行くことが何よりも大切ではないでしょうか?
後日「こんな筈ではなかった」と後悔しないためにもこのことは重要です。