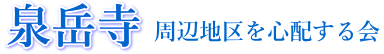不安商法とは、その名の通り不安を煽ることで相手先から契約を獲得しようとする不当な商いのやり方を言います。
不動産取引で「不安商法」と言えば、リフォーム工事業者が住宅へやって来て、住民に対して地震への不安などを煽り、不当に高額な工事を行なわせると言った事例を思い浮かべることが多いのではないでしょうか?
再開発事業でも事業者による似たような手口が散見されます。
しかも再開発に至ってはリフォーム工事どころの話ではありません。土地・建物の資産全体が取引対象となるだけに事態はより深刻です!安易に業者の仕掛ける「不安商法」に乗ってしまうと、後日、「こんな筈ではなかった!」と後悔することになりかねません。
業者は防災面での不安を煽ることが多い
先ずは、このことをしっかりと心に留めておいて下さい。
そもそも再開発事業者が目をつける地域は、老朽化した建物が建ち並ぶ地域が多く、とりわけ今も各地で点在する「木造住宅密集地域」と言われるエリアは、業者が防災面での不安を煽る格好のターゲットとなります。
再開発事業者が再開発(第一種市街地再開発事業)を進めるためにはどうしても「地権者の同意」を取得する必要があります。このため一部のコンプライアンス意識の欠如した再開発業者は防災面での不安を過度に煽り立てることで、地権者を再開発へ誘導しようと試みるのです。
これが再開発業者の「不安商法」のメカニズムです!
地権者としてはこの手法を知っておく必要があります。
例えば、再開発事業者が地権者宅を訪問するなどして、地震や火災等の防災面への不安を過度に煽り、再開発への同意を得ようとしたならば、まさにそれは不当な「不安商法」だと疑ってみて下さい。
もし、住友不動産のような大手企業がこのような行為に及ぶとすれば問題です。業界大手ともなれば、社員が遵守すべきコンプライアンスや倫理規定も社内で明文化されている筈ですし、また彼らが活動を行なう際には、契約者の利益の保護等を目的に制定された宅地建物取引業法(略称:宅建業法)の精神を遵守することが不動産業者として当然求められます。しかし、残念なことに、例え業界大手企業であっても、「不安商法」を用いて地権者を再開発同意へ追い込もうとする業者が存在するのが現実です。しかも彼らは責任回避を狙ってか、自社名を表に出すことなく、常に「準備組合」と言う任意団体の名の下で活動を行なおうとするので、この点にも注意が必要です。
「不安商法」から資産を守るには?
では、地権者が業者による「不安商法」から大切な資産を守るためにはどうすれば良いのか?
結論としては、やはり自身で正しい「知識」や「知見」を積極的に身につけ、偉大なる「常識」を駆使して真偽を見極めることに尽きるのではないでしょうか?また見極めに際しては、家族や友人、場合によっては専門家とよく話し合うことも大切です。
「三人寄れば文殊の知恵」と言いますが、三人集って話し合えば、後日「こんな筈ではなかった」と後悔する可能性も低くなる筈です。
先ずは地元の「災害危険度」を知ろう!
再開発事業者は、防災面での不安を過度に煽ってくることがあります。これを見破るには、地元エリアの危険度がどの程度なのかを自身で知っておくことが何よりも大切です。
たとえば「木造住宅密集地域」と言われるエリアの場合、事前に調べていなければ、どうしても外見だけを見て災害面での危険度が高いように思ってしまいます。そこへ再開発業者がやって来て「地震が来たら倒壊しますよ」、「火災時には燃え広がりますよ」、「狭い通路には消防車が入れませんよ」、などと煽り立てれば地権者は再開発しか選択肢はないなどと思い込んでしまいがちです。
しかし、本当にその通りなのでしょうか?
再開発業者の言うことを鵜呑みにしてはいけません!
多くの自治体では「災害危険度マップ」と言った類いの情報を公開しています。先ずは自分の住む地域の危険度がどの程度なのかを、公的機関が発行する客観的資料で確認した上で、再開発業者の言質が真実なのか否かを冷静に見極めるべきです。
再開発業者が発する情報が、実は公的機関の情報と大きく異なっていたと言うケースもあります。再開発業者の言うことを鵜呑みにすべきではありません。
因みに、私たちが住む東京都港区でも各所に「木造住宅密集地域」が点在していますが、実際にこれらの地域で再開発業者が防災面での不安を煽るケースが複数報告されています。
しかし、このような業者の行為は極めて不誠実だと言わざるを得ません。
何故なら、東京都が公表した災害危険度マップを見ると、港区内にはいわゆる「危険度が高い」(5段階評価で危険度4~5)とされる地区は一つも存在しないからです!
再開発業者の言質を決して鵜呑みにすべきではない理由がここにあります。
まとめ
残念なことに、いまも地震や火災への不安を過度に煽ることで地権者を再開発賛成へ仕向けようとする不誠実な再開発業者が存在します。決して彼らの手口に乗ってはいけません。
後日後悔しないためには、自ら積極的に情報を収集することで業者の説明が真実なのか、それとも芝居なのかを見極める必要があります。
地元の「災害危険度」について調べ、具体的状況を知っておくことはとても重要です。多くの自治体では「災害危険度マップ」などの情報を公開していますので、先ずはそちらを確認されてみては如何でしょうか?