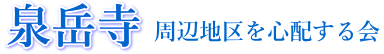本トピックスは(265)及び(266)からの続きです。前トピックスでは業者の「誤った説明」事例を取り上げ、地権者へ注意喚起を行いました。
では業者側に「誤った説明」をさせないためにはどうしたら良いのか?
本トピックスではこの点について考えて参ります。(注1)
1. 地権者が忘れてはならないこと
2. 不動産鑑定士による誘導にはご注意
3. 業者は鑑定士を都合よく利用している?
4. 地権者側の対策
5. まとめ
地権者が忘れてはならないこと
再開発業者側に「誤った説明」をさせないために忘れてはならないこと。
それは
「従前評価方針」、「保留床単価」、「増床ルール」と言った
基本事項の決定権は地権者側(=組合側)にある
と言う点を地権者一人一人がしっかり自覚する点にあります。(注2)
再開発(第一種市街地再開発事業)は地権者が事業主体となって進める事業ですから当然のことです。業者側が決定するのではありません!
不動産鑑定士による誘導にはご注意!
不動産鑑定士は国家資格です。それだけに一般の地権者は「鑑定士が言うのだから」と鑑定士の発言を安易に信じてしまいがちです。しかし、その考えは改めるべきです。不動産鑑定士が行う評価やコメントは「依頼人が誰か」により大きく数字や内容が異なるからです。(注3)
多くの傀儡型組合では「事務局」業務を担う再開発業者が自社寄りの不動産鑑定士を特命で採用する傾向が顕著です。その見分け方は簡単です。採用にあたり「複数の鑑定会社から見積もりを取得し、比較検討を行ったか否か」が判断基準ですので素人にもわかります。鑑定会社間の競争もなく特命で採用された鑑定士は地権者ではなく再開発業者側の意向を忖度して鑑定評価等を行うので地権者は要注意です。(注4)
業者は鑑定士を都合よく利用している?
再開発業者の目的は開発利益(=保留床)を最大化することにあります。この目的を達成するために業者は不動産鑑定会社を使い、地権者をカモる目的で「3本の矢」(注5)を放つことがわかってきています。
(199)地権者をカモる3本の矢!
(211)地権者をカモる3本の矢!(続編)
これら「3本の矢」を簡単に説明すると、
【1本目】 「開発利益なしの従前評価方針」は、業者が開発利益を独占する(=地権者には利益を与えない)ための「一方的な説明」です。
【2本目】 「激安保留床単価の既成事実化」は保留床面積を最大限確保したい業者が考案した策略で、単価が安いほど保留床面積は増える一方で、権利床面積はその分減るため地権者は損をすることになります。
【3本目】 「増床制限」は保留床面積を減らしたくない再開発業者が地権者側による「床の追加取得」に制限をかけようとするものです。
上記は何れも「地権者が事業主体」であることを軽視した「誤った説明」、「誤った方針」であるため、地権者から異議申し立てが行われても再開発業者側は正論で説明を行うことが出来ません。そこで業者側は敢えて国家資格を有する不動産鑑定士に説明させることで地権者を煙に巻き、自論を正当化させようとするのだと考えられます。
例えば「激安保留床単価」に関して言えば、もし再開発業者(=民間の不動産会社)の立場で直接このような理不尽な主張を行えば地権者の反発は必至です。しかし、国家資格を持つ不動産鑑定士に「鑑定評価でこう算定されている」などと発言させれば、地権者の懐柔をはかることが可能となり、結果として実勢相場より著しく安い単価を正当化できるというのが業者側の目論見です。
このようにして再開発業者は、不動産鑑定士の業務範囲を「鑑定」のみならず、「総額」や「単価」、更には「算定ルール」まで包括的に「鑑定士の権限」に仕立て上げることで、鑑定士を利用して事業全体をコントロールする体制を構築しようとするので地権者はお気を付けください。(注6)
(注6)本トピックスでは「不動産鑑定士」に焦点を当てていますが、再開発業者側に特命で採用される「コンサル」等も不動産鑑定士とほぼ同様の行動をとる傾向が見られますのでご注意ください。
地権者側の対策
では、地権者側はどのように対応すればよいのか?
先ずは、再開発業者が競争によらず特命で自社寄りの不動産鑑定士等を採用する「不透明なプロセス」そのものを問題視してください。
次に、業者が儲ける仕組みを不動産鑑定士を通じて既成事実化させようとする再開発業者の手口そのものを問題視してください。
評価額や単価、更には再開発のルールに至るまでの全てを「国家資格を持つ鑑定士の権限」に仕立て上げれば、再開発業者は鑑定士を通じ、労せずして事業をコントロールできる仕組みが出来上がるため、地権者側は何としてもこれを阻止する必要があります。
対策の一つとして、不動産鑑定士の業務範囲を予め限定してしまう方法が考えられます。
例えば、従前評価に関して言えば、
「従前評価 = (保留床単価×総専有面積)-補助金控除後事業費」
と言うように、組合側(=地権者側)が計算式を先に決めてしまうことです。
また保留床単価に関して言えば、
「保留床単価 = 近隣地区の分譲相場×70~80%とする」
と言ったように組合側が算定ルールを先に決めてしまうことです。
このように組合(=地権者)側にて「計算式」や「適用ルール」を先に決めてしまうことで不動産鑑定士が操作する余地を大幅に減らすことが可能となります。
まとめ
再開発業者から見れば、国家資格を有する「不動産鑑定士」は利用価値が高く、鑑定士を「従前評価」、「激安保留床単価」、「増床」の3点すべてにおいて地権者との交渉窓口に据えることは有効な戦略となります。
しかし地権者にとっては逆であり、鑑定士の役割を「最低限必要な業務」に限定することこそが有効な防御策となります。(例えば鑑定士の役割を、既に決まった「従前評価額」の配分作業に専念させるなど。)
しかし「言うは易く行うは難し」です。百戦錬磨の再開発業者を相手に決して交渉は簡単ではありません。地権者を煙に巻く弁解や詭弁が次々と出て来る可能性があるからです。そこでの対策として、
おかしな説明がなされたと思ったら
必ず業者から「書面による説明」を取り付ける
ことを心掛けてください。
書面で説明を取り付ければ後日冷静に内容を検討することが出来ますし、不明点があれば弁護士等の専門意見を仰ぐことも可能となります。
また書面を取り付ければ、後日「言った、言わない」で揉める懸念もなくなります。更に書面は記録として残るため、業者側も安易に「誤った説明」を行うことが出来なくなると言った抑制効果も期待できます。
百戦錬磨のプロ集団を相手に、素人集団である地権者たちにできる対策は限られます。しかし、だからと言って高度な専門知識が要求されるわけでもありません。一般市民として長年の社会生活の中で培った「常識」、「良識」、そして「見識」をフルに活かし、
「公平、公正、透明性ある計画推進」に徹底してこだわる
ことで、名実ともに地権者が主体となる再開発事業を実現させることは決して不可能なことではありません。
そして何よりも大切なこと。それは、
自身で理解し納得しない限り
決して再開発への同意を行わない
と言う点です。
一定割合の「地権者同意」が集まらない限り再開発が進むことはありません!
これこそが地権者が持つ最大の武器だと言えるのではないでしょうか?